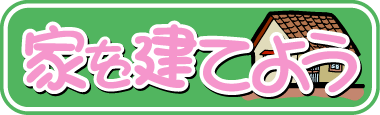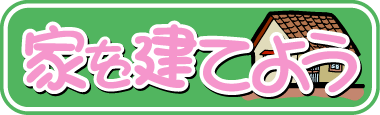|
2
|
(日本人)日本国籍所持者か一定の条件を満たした外国人であること。
|
|
3
|
申込日現在、70歳未満であること。
ただし、以下の条件すべてに当てはまる連帯債務者(後継者)でローン返済を継承する場合であれば可。
(1)本人の子供であること(子供がいない場合は、配偶者以外の親族でもよい)
(2)同居か将来同居すること
(3)後継者が70歳以下であること
(4)公庫融資を受けていないこと
|
|
4
|
毎月の返済額の五倍以上収入があること。
ただし、満たない場合でも以下の条件にすべて当てはまる同居人(予定者)の月収を必要月収の半分まで合算できます。 (本人の月収額と同額が限度)
(1)直系親族か婚約者であること
(2)連帯債務者になること
(3)70歳未満であること
また、四倍以上の収入があれば住宅債券積み立てを利用できます。
|
ここまで条件を満たせば利用者条件はクリアです。
次に住宅の条件です。

建てる住宅の条件
|
1
|
住居専用か店舗付き住宅。
店舗付きの場合、 入居者が店舗を使用し住宅部分の*床面積が店舗の半分以上であること。
|
|
2
|
住宅部分の*床面積が約24〜85坪以内であること。
敷地が約30坪以上であること。
上記条件以外でも、公共事業による移転一年以内に災害で住居を失った・過疎地域活性化特別 処置などによる移転・昭和57年1月2日以後に分筆、分割していない敷地、等に当てはまれば融資を受けることができます。
|
|
3
|
建設費が公庫の定める限度額以内であること。
公庫融資個人住宅建設基準に適合 。
|